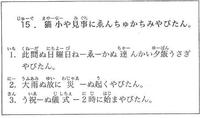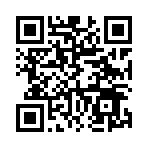2010年07月03日
7月2日(金)“第14回 喜多見で沖縄語を話す会”
“喜多見で沖縄語を話す会”の活動報告を、(株)M.A.P.のブログ「M.A.P.after5」からこちらの専用ブログへ引き継ぐことにしました。
※なお第14回以前の記事は、第1回の記事から順番に読むことができます。
⇒第1回“喜多見で沖縄語を話す会”(M.A.P.after5)
というわけで7月2日(金)の勉強会の報告です。
“第14回 喜多見で沖縄語を話す会”
早いもので(会話練習11)になりました。
昨日の勉強は
①疑問詞の使い方(その3)
「何時(いち)」
「幾ち(いくち)」
の使い方を勉強しました。
一例をご紹介します。
……………………………………………………………………
例:「あなたは何時沖縄へ行きましたか?」
(沖縄語訳)
「うんじょー、いち うちなーかい めんそーちゃが?」
……………………………………………………………………
※うんじゅ(あなた)、うんじょー(あなたは)
※いち(いつ)
※うちなー(おきなわ)
※かい(~に)
目的がはっきりしている場合(~かい)
目的があいまいな場合 (~んかい)
と使い分けることがあったそうですが、最近はうやむやになってきているそうです。
※めんそーる(「行く・来る」の丁寧語)
めんそーちゃん(過去形)
※~が(ですか?)
といった具合です。
【脱線ゆんたくコーナー@7月2日】
昨日はウコー(御香)とウチカビ(紙銭)と亀甲墓の話でした。
沖縄の線香といえば、黒いイモクズで作られたヒラウコー(平御香)が有名です。
平御香(ヒラウコー)は6本の線香が連なって板状になって1本になっている帯条の御香で、
トートーメー(御元祖)や墓のご先祖様に、一番最初にお線香をあげるときには、
ご先祖様全員に向けてお線香をささげるといういう意味で「十二支」の分で12本、
ヒラウコーは6本セットなので、ヒラウコー2本で12本のお線香をささげるのですが、
数え方が、
ヒラウコー1本(イップン)
ヒラウコー2本(ニフン)
ヒラウコー3本(サンブン)
「ヒラウコー2本(ニフン)で、12本(ジュウニフン)」
とか、
また沖縄ではあの世のお金として、ウチカビ(紙銭)を焼くという話になったら
沖縄で「私の実家でウチカビを作っていました!」という方が勉強会のメンバーにいて
ウチカビの作り方を教えていただいたり、
お盆のときにトートーメーにお供えするサトウキビは
あの世の人が使う杖で、八重山のアンガマ踊り(あの世の人たちが帰ってきて踊る)
のあの世から戻ってきた沖縄たちの踊りでも、サトウキビの杖をついて登場して
踊りを踊るとか、
あの世にお土産を持って帰るとき、頭に荷物を載せてかえるが、
その時の荷物の台座を「ガンシチナー」といって、お盆のときに、スイカを載せる円座のようなものを作って、あれも、あの世の人が使うのだとか。
東京のお盆はまもなくですが、オキナワは旧盆で約一月遅れでお盆があります。
お盆の踊りが「エイサー踊り」で、そろそろエイサーの季節ですね。
■次回の勉強会の日程
次回は「8月6日(金)19時~21時」です。
⇒第15回の記事へ
……………………………………………………………………
【おまけ】
うんじゅが情けどぅ頼まりる
※なお第14回以前の記事は、第1回の記事から順番に読むことができます。
⇒第1回“喜多見で沖縄語を話す会”(M.A.P.after5)
というわけで7月2日(金)の勉強会の報告です。
“第14回 喜多見で沖縄語を話す会”
早いもので(会話練習11)になりました。
昨日の勉強は
①疑問詞の使い方(その3)
「何時(いち)」
「幾ち(いくち)」
の使い方を勉強しました。
一例をご紹介します。
……………………………………………………………………
例:「あなたは何時沖縄へ行きましたか?」
(沖縄語訳)
「うんじょー、いち うちなーかい めんそーちゃが?」
……………………………………………………………………
※うんじゅ(あなた)、うんじょー(あなたは)
※いち(いつ)
※うちなー(おきなわ)
※かい(~に)
目的がはっきりしている場合(~かい)
目的があいまいな場合 (~んかい)
と使い分けることがあったそうですが、最近はうやむやになってきているそうです。
※めんそーる(「行く・来る」の丁寧語)
めんそーちゃん(過去形)
※~が(ですか?)
といった具合です。
【脱線ゆんたくコーナー@7月2日】
昨日はウコー(御香)とウチカビ(紙銭)と亀甲墓の話でした。
沖縄の線香といえば、黒いイモクズで作られたヒラウコー(平御香)が有名です。
平御香(ヒラウコー)は6本の線香が連なって板状になって1本になっている帯条の御香で、
トートーメー(御元祖)や墓のご先祖様に、一番最初にお線香をあげるときには、
ご先祖様全員に向けてお線香をささげるといういう意味で「十二支」の分で12本、
ヒラウコーは6本セットなので、ヒラウコー2本で12本のお線香をささげるのですが、
数え方が、
ヒラウコー1本(イップン)
ヒラウコー2本(ニフン)
ヒラウコー3本(サンブン)
「ヒラウコー2本(ニフン)で、12本(ジュウニフン)」
とか、
また沖縄ではあの世のお金として、ウチカビ(紙銭)を焼くという話になったら
沖縄で「私の実家でウチカビを作っていました!」という方が勉強会のメンバーにいて
ウチカビの作り方を教えていただいたり、
お盆のときにトートーメーにお供えするサトウキビは
あの世の人が使う杖で、八重山のアンガマ踊り(あの世の人たちが帰ってきて踊る)
のあの世から戻ってきた沖縄たちの踊りでも、サトウキビの杖をついて登場して
踊りを踊るとか、
あの世にお土産を持って帰るとき、頭に荷物を載せてかえるが、
その時の荷物の台座を「ガンシチナー」といって、お盆のときに、スイカを載せる円座のようなものを作って、あれも、あの世の人が使うのだとか。
東京のお盆はまもなくですが、オキナワは旧盆で約一月遅れでお盆があります。
お盆の踊りが「エイサー踊り」で、そろそろエイサーの季節ですね。
■次回の勉強会の日程
次回は「8月6日(金)19時~21時」です。
⇒第15回の記事へ
……………………………………………………………………
【おまけ】
うんじゅが情けどぅ頼まりる
Posted by はいさい狛江 at 10:43│Comments(0)
│活動報告